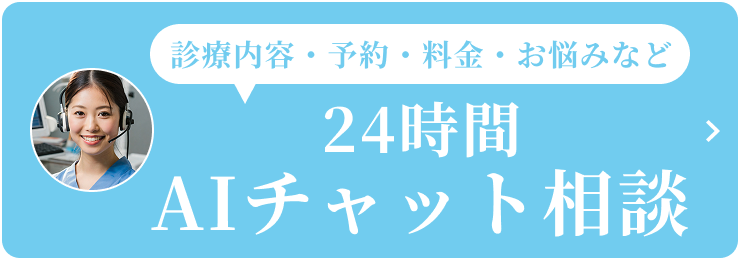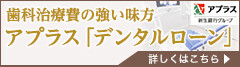こんにちは。愛知県名古屋市名東区にある歯医者「西山歯科」です。

歯周病は、歯を失う原因として虫歯と並び非常に多い病気です。初期の段階では痛みがほとんどなく、気づかないうちに進行することが特徴です。放置すると歯ぐきや歯を支える骨がダメージを受け、最終的には歯を失うリスクもあります。
この記事では、初期の歯周病に見られる主な症状と、進行を防ぐための治療法や予防法について詳しく解説します。
目次
歯周病とは?
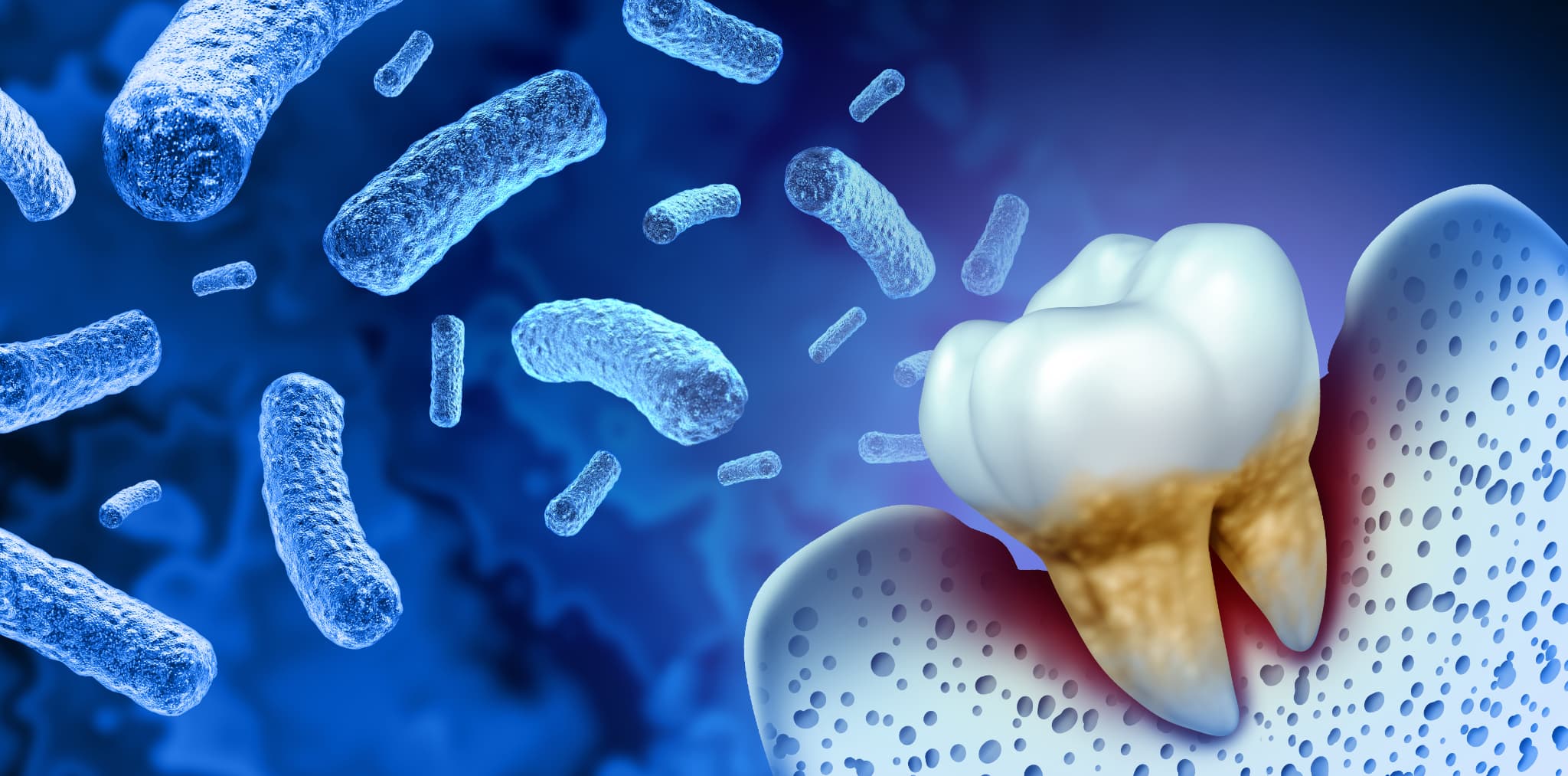
歯周病は、歯を支える歯ぐきや歯槽骨などの組織に炎症が起こる病気です。歯と歯ぐきの境目にたまった歯垢(プラーク)の中にいる細菌が原因で発症し、初期段階では歯ぐきの腫れや出血といった軽い症状から始まります。
進行すると歯を支える骨が破壊されて歯がぐらつき、最終的には抜歯が必要になる場合もあります。
歯周病は自覚症状が出にくいため、気づかないうちに進行しているケースが多いのが特徴です。特に、歯肉炎や軽度の歯周炎では痛みがほとんどないため、症状を放置しやすく、気づいたときには中等度以上に悪化していることも珍しくありません。
歯周病の発症には、歯垢や歯石の蓄積に加え、喫煙やストレス、糖尿病などの生活習慣や全身疾患も影響します。予防や進行防止には、毎日の丁寧な歯磨きと定期的な歯科検診が欠かせません。歯ぐきの健康を保つためには、早期発見・早期治療が重要です。
初期の歯周病に見られる主な症状

歯周病は、進行してからでは治療が複雑になりやすいため、初期段階での気づきが重要です。
しかし、初期の歯周病は痛みなどの強い自覚症状がほとんどないため、見落としやすいです。ここでは、早期発見のために知っておくべき代表的な症状を解説します。
歯ぐきの腫れや赤み
初期の歯周病では、歯と歯ぐきの境目に炎症が起き、歯ぐきが赤く腫れます。健康な歯ぐきは淡いピンク色で引き締まっていますが、炎症があると色が濃くなり、触れると柔らかさを感じることもあります。
この変化は痛みを伴わないことが多く、鏡で確認しないと気づきにくいです。
歯磨きや食事中の出血
歯ブラシやデンタルフロスを使った際に血がにじむのも、初期の歯周病でよく見られるサインです。「強く磨きすぎたせい」と思われがちですが、実際には歯ぐきの炎症によるものが多く、放置すると炎症が進行する原因になります。
出血が繰り返し見られる場合は、早めの受診を検討しましょう。
口臭の悪化
歯周病が始まると、歯と歯ぐきの境目に歯垢や細菌がたまりやすくなり、これが原因で口臭が強くなることがあります。口臭ケアをしても改善しない場合、歯周病の可能性を疑う必要があります。
歯ぐきのむず痒さや違和感
初期段階では強い痛みは出ませんが、歯ぐきに軽いむず痒さや圧迫感を感じることがあります。こうした小さな異変は、歯周病のサインである場合があります。
初期段階の歯周病の治療法

歯周病は進行性の病気ですが、初期段階であれば簡単な処置で改善が期待できます。痛みがほとんどないため放置されやすいものの、早期に適切な治療を行うことで、健康な歯ぐきと歯を取り戻せます。
ここでは、初期段階で行われる主な治療方法を詳しく解説します。
プロフェッショナルクリーニング
初期段階の歯周病は、歯と歯ぐきの境目に歯垢や歯石が付着し、そこに細菌が繁殖することで炎症が起こります。歯石は時間が経過すると硬くなり、通常の歯磨きでは除去できません。そのため、歯科医院でのスケーリング(歯石除去)が治療の基本となります。
スケーリングでは、専用の超音波スケーラーや手用スケーラーを使って、歯の表面や歯周ポケット内に付着した歯石を丁寧に取り除きます。細菌の温床となる歯石を除去することで、炎症が改善され、歯ぐきの腫れや出血が徐々におさまっていきます。
ルートプレーニング
初期歯周病であっても、歯周ポケットがやや深くなっている場合には、スケーリングに加えてルートプレーニングという処置を行うことがあります。これは、歯根表面にこびりついた歯石や汚染物質を取り除き、滑らかな状態に整える治療です。
歯根の表面がザラザラしていると、細菌や歯垢が再付着しやすく、炎症の再発リスクが高まります。ルートプレーニングによって歯根をツルツルにすることで、細菌が付きにくくなり、歯周組織の再付着を促進できます。
正しいブラッシング指導
歯周病は、一度治療を受けても、日常のセルフケアが不十分だと再発しやすいです。そのため、歯科医院では必ずブラッシング指導が行われます。歯並びや歯ぐきの状態に合わせた磨き方を学ぶことは、プラークコントロールをする上で不可欠です。
また、歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシの正しい使い方も指導されます。歯と歯の間や歯ぐきの境目は、歯周病の原因となるプラークが溜まりやすい場所です。適切な清掃方法を身につけることで、再発防止と歯周病予防の効果が高まります。
定期的なメンテナンス
治療後に改善が見られても油断は禁物です。生活習慣やブラッシングの乱れがあると、再び歯垢や歯石が溜まり、炎症が再発することがあります。そのため、歯科医院での定期的なメンテナンスは欠かせません。
通常は、3〜6か月ごとにプロフェッショナルケアを受けることが推奨されます。定期検診では、歯ぐきの状態を確認し、必要に応じてスケーリングや歯面清掃を行います。
歯周病を予防するためには

以下に、歯周病を防ぐために実践したい具体的なポイントを紹介します。
毎日の正しいブラッシングを徹底する
歯周病予防の基本は、歯垢(プラーク)を取り除くことです。歯垢は細菌のかたまりで、放置すると歯ぐきの炎症や歯石の原因になります。予防には1日2〜3回のブラッシングが欠かせませんが、単に磨くだけではなく、正しい方法を実践することが重要です。
毛先が歯と歯ぐきの境目に軽く触れるように45度の角度で当て、小刻みに動かすバス法を取り入れましょう。力を入れすぎると歯ぐきを傷つける原因になるため、やさしく磨くことを意識してください。
また、歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れを取りきれないため、デンタルフロスや歯間ブラシも取り入れると効果的です。
食生活の見直しと生活習慣の改善を図る
食生活は歯周病の予防に大きな影響を与えます。砂糖を多く含む食品や間食が多いと、口の中が酸性になり、細菌が繁殖しやすくなります。間食を控え、バランスの取れた食事を意識することが重要です。
特に、野菜やたんぱく質を含む食品は、歯や歯ぐきの健康維持に役立ちます。
さらに、喫煙は歯周病を悪化させる最大のリスク要因の一つです。タバコに含まれる有害物質は血流を悪化させ、歯ぐきの治癒力を低下させます。歯周病予防のためには禁煙が不可欠です。
また、過度なストレスや睡眠不足も免疫力を下げ、歯周病の発症リスクを高めるため、規則正しい生活を心がけましょう。
定期的な歯科検診でクリーニングを受ける
セルフケアだけでは完全に歯垢や歯石を取り除くことはできません。特に、歯周ポケットの奥に入り込んだ歯石や汚れは歯科医院での専門的なクリーニングが必要です。3〜6か月に1回の定期検診を受けることで、歯周病の早期発見と予防につながります。
歯科医院ではスケーリングやルートプレーニングなどの処置を行い、歯周病の原因となる汚れを徹底的に除去します。また、歯科医師や歯科衛生士によるブラッシング指導を受けることで、自宅でのケアの質を高められます。
フッ素や抗菌剤を活用する
フッ素は、歯の再石灰化を促進し、エナメル質を強化する働きがあります。このため、虫歯や歯周病の予防に非常に有効です。歯科医院で受けられる高濃度フッ素塗布は、特に子どもや初期段階の歯周病予防に効果的です。
また、自宅でのケアでもフッ素入り歯磨き粉を継続的に使うことで、毎日のブラッシングがより効果的になります。
さらに、歯周病の進行を防ぐためには、抗菌作用のある洗口剤を取り入れるのも有効な手段です。洗口剤は、口腔内の細菌数を減らすことで炎症を抑え、歯ぐきの健康維持に役立ちます。
ただし、洗口剤はあくまで補助的なケアであり、歯ブラシによる機械的な清掃に代わるものではありません。
全身の健康管理も行う
歯周病は単なる口の中の病気ではなく、全身の健康にも深く関わっています。特に糖尿病や心疾患、動脈硬化といった生活習慣病は、歯周病と相互に悪影響を及ぼすことが知られています。
そのため、歯周病予防には、口腔ケアだけでなく全身の健康管理も欠かせません。バランスの取れた食生活、十分な睡眠、ストレスの軽減といった基本的な生活習慣を見直すことが重要です。
まとめ

歯周病は、痛みがほとんどないまま進行するため、気づいたときには中等度以上になっていることも少なくありません。初期段階では歯ぐきの腫れや出血、口臭などの軽い症状が現れますが、この時点で適切なケアを行えば改善が期待できます。
治療には歯科医院でのスケーリングやブラッシング指導が有効で、再発防止には定期検診と毎日の丁寧なセルフケアが欠かせません。大切なのは放置しないことです。歯ぐきに違和感を感じたら、早めに歯科医師に相談し、将来の歯を守る第一歩を踏み出しましょう。
歯周病の治療を検討されている方は、愛知県名古屋市名東区にある歯医者「西山歯科」にお気軽にご相談ください。
当院では、一般歯科や小児歯科、ホワイトニング、インプラント、矯正治療など、さまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、WEB予約も受け付けておりますので、ぜひ参考にしてください。