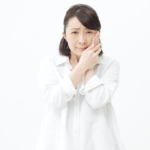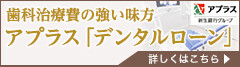こんにちは。愛知県名古屋市名東区にある歯医者「西山歯科」です。

顎の関節に違和感を覚えたり、口を開けるとカクカク音がしたりする症状を経験したことはありませんか。そのような症状がある場合、顎関節症の可能性があります。
初期段階では些細な違和感にとどまることもありますが、放置すると日常生活に大きな支障をきたすことがあるため注意が必要です。
今回は、顎関節症を放置することによるリスクや原因、治療法について詳しく解説します。顎の異変を感じている方や、顎関節症の知識を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
顎関節症とは

顎関節症(がくかんせつしょう)とは、顎の関節やその周辺の筋肉に異常が生じることで、口の開閉時に痛みや違和感を引き起こす疾患です。
顎関節症になると、顎関節やその周囲が痛む、口を開けにくくなる、顎の関節から音がする、噛み合わせに違和感を覚えるなどといった症状が現れます。
発症の原因は多岐にわたり、噛み合わせの不良、歯ぎしり、ストレス、姿勢の悪さなどが複合的に関係しています。また、女性に多く見られる傾向があり、特に20〜40代の女性に多いとされています。
顎関節症は命に関わる病気ではありませんが、慢性化すると日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。そのため、症状が現れはじめた段階で適切な治療を受けることが非常に重要です。
顎関節症を放置するリスク

顎関節症を放置すると、さまざまな健康上のリスクが生じる可能性があります。以下に代表的な影響をご紹介します。
噛み合わせが悪くなる
顎関節症を放置しておくと、噛み合わせが徐々にずれる可能性があります。
顎の関節や筋肉に異常がある状態では、自然な位置で噛むことが難しくなり、無意識のうちに偏った噛み方をするようになります。その結果、上下の歯の接触が不均一となり、さらに顎への負担が増大します。
噛み合わせの乱れは、歯の摩耗や顎関節のさらなる悪化を引き起こし、治療が複雑になることもあります。
食事がしづらくなる
顎関節症が進行すると、口を開けるたびに痛みや違和感が生じ、スムーズに食事をすることが困難になります。特に硬いものや大きなものを噛む動作が制限されるため、食生活が偏ってしまう原因にもなります。
また、痛みを避けるために片方の歯でばかり噛むようになり、さらに噛み合わせのバランスが崩れるという悪循環にいたるケースもあるでしょう。
頭痛や肩こりを引き起こす
顎関節症によって顎の筋肉が緊張状態になると、頭部や首、肩にまで影響が及ぶことがあります。
特に顎の筋肉と首周りの筋肉は密接に関係しており、慢性的な肩こりや頭痛の原因となることもあります。これらの症状は、一般的な肩こりや片頭痛と見分けがつきにくく、適切な治療を受けないまま長引くこともあります。
そのため、原因不明の頭痛が続いている場合は、顎関節症を疑う必要があるかもしれません。
口を開けにくくなる
症状が悪化すると、口を大きく開けることが困難になり、あくびや会話、歯磨きなど日常の動作に支障をきたします。口を開ける際にカクンという音がしたり、痛みを伴ったりする場合もあります。
さらに進行すると、顎が引っかかったような感覚になり、開閉がほとんどできなくなることもあります。このような状態になると、食事や会話すら困難になり、生活の質が大きく低下してしまいます。
生活の質が低下する
顎関節症を放置することで、日常生活全体に支障が出るようになります。
食事や会話がしづらい、頭痛や肩こりが慢性化するなど、さまざまな問題が積み重なり、精神的なストレスや不安感を抱えることにもつながります。また、外出や人とのコミュニケーションを避けるようになり、社会生活にも悪影響を及ぼすことがあります。
このように、顎関節症は単なる顎の不調にとどまらず、全身および心理面にも影響を及ぼす重大な問題なのです。
顎関節症の原因

次に、顎関節症の主な原因について理解を深めましょう。複数の要因が複雑に絡み合って発症することが多いため、原因を正しく知ることが予防や治療の第一歩となります。
噛み合わせが悪い
上下の歯が正しく噛み合っていないと、顎の筋肉や関節に偏った力がかかり、負担が蓄積されます。これにより、顎関節が正常な動きを失い、痛みや異音などの症状が現れることがあります。
特に、歯列矯正が必要なレベルの不正咬合を放置していると、顎関節への悪影響が顕著になる傾向があります。
歯ぎしりや食いしばり
就寝中の歯ぎしりや日中の食いしばりも、顎関節症の大きな原因の一つです。これらの無意識の動作は、顎の筋肉に強い緊張を与え、関節への過度な負荷となります。
特にストレスを感じているときに無意識に行われやすく、放置すると顎関節だけでなく歯の摩耗や歯周病のリスクも高まります。
悪い姿勢
長時間のスマートフォン操作やデスクワークによって猫背や前傾姿勢が続くと、顎の位置もずれてきます。顎は首や背中と連動しているため、姿勢の悪さは顎関節への負担を増やす要因となります。
特に下顎が前に出るような姿勢が続くと、関節に異常な圧力がかかり、顎関節症を引き起こしやすくなります。
ストレス
ストレスも顎関節症の原因として見逃せません。精神的な緊張状態が続くと、無意識のうちに歯を食いしばる癖がつき、それが顎関節に悪影響を与えます。また、ストレスは筋肉の緊張や血流の悪化を招き、顎関節症の症状を悪化させることがあります。
そのため、ストレスを管理することは顎関節症の予防や改善において非常に重要なのです。
生活習慣の乱れ
睡眠不足や栄養バランスの偏り、運動不足などの生活習慣の乱れも顎関節症の発症リスクを高めます。
体調が不安定になると、筋肉や関節の機能も低下し、顎関節に不調が現れやすくなります。規則正しい生活を心がけることで、身体全体の健康を保つとともに、顎関節への負担も軽減することができます。
顎関節症の治療法

顎関節症は、原因や症状の程度に応じてさまざまな治療法が選択されます。ここでは代表的な治療法をご紹介します。
生活習慣の改善
最も基本的な治療の一つが、生活習慣の改善です。例えば、無意識の食いしばりを避けるためにリラックスする時間を増やすこと、長時間同じ姿勢で過ごさないようにすることが挙げられます。
また、柔らかい食べ物を中心に食べ、顎に過度な負担をかけないように配慮することも重要です。十分な睡眠やストレス管理も症状の軽減に大きく関与します。
生活習慣を整えることで、軽度の顎関節症であれば症状が自然と改善するケースもあります。
スプリント療法
スプリント療法とは、マウスピース型の装置を口の中に装着し、顎関節や筋肉への負担を軽減する治療法です。
夜間に装着することで、歯ぎしりや食いしばりから顎を守り、関節や筋肉を休ませる効果があります。また、噛み合わせの調整にも役立ち、顎関節の位置を正常に保つことができます。
理学療法
理学療法では、顎周辺の筋肉の緊張をほぐしたり、関節の動きを改善したりするためのマッサージやストレッチ、温熱療法などが行われます。顎関節に直接働きかけることで、痛みの緩和や可動域の改善を目指します。
軽度から中等度の症状に有効で、副作用の心配も少ないため、安心して受けられる治療の一つです。
薬物療法
痛みや炎症が強い場合には、薬物療法が行われることもあります。一般的には痛みを和らげる非ステロイド性抗炎症薬や、筋肉の緊張をほぐす筋弛緩薬などが処方されます。
これらはあくまで症状の一時的な緩和を目的とした治療法であり、根本的な改善にはほかの治療法と組み合わせることが推奨されます。薬に頼りすぎず、並行して生活習慣の見直しや理学療法を受けることが大切です。
まとめ

顎関節症は、日常生活に潜むさまざまな要因によって引き起こされる疾患であり、放置すると噛み合わせの悪化、食事の困難、頭痛や肩こり、生活の質の低下など多くの問題を引き起こします。
しかし、早い段階で適切な治療を受ければ症状の改善が見込めます。まずは自分の顎に違和感がないかを見直し、気になる症状があれば早めに歯科医師に相談することが重要です。
顎関節症は、自分の生活習慣やストレス管理とも深く関係しています。日頃から予防の意識をもち、症状が現れた際には早期の対応を心がけましょう。
顎関節症の症状にお悩みの方は、愛知県名古屋市名東区にある歯医者「西山歯科」にお気軽にご相談ください。
当院では、一般歯科や小児歯科、ホワイトニング、インプラント、矯正治療など、さまざまな診療を行っています。
ホームページはこちら、WEB予約も受け付けております。公式Instagramも更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。